以下の方におすすめの記事です。
・普通預金以外に低リスクでお得な貯蓄方法を探している方。
・投資信託や個別株など元本割れするリスクのある商品は怖いと思っている方。
国の政策金利も徐々に上がっており、普通預金の金利も以前よりもやや旨みが出てくるようにはなりました。
2025年現在で大手銀行で0.2%程度の金利、100万円預けていたら2000円が利息としてもらえます。
数年前までは0.001%程度の金利、同じ金額を預けてても10〜20円しかもらえなかったことを考えると嬉しいといえば嬉しいですね。
それでも寝かせているお金にはもっと働いてほしいと思っている人もいるはず。
そんな方のために普通預金よりも金利が高い・元本保証されている商品をまとめてご紹介します。
普通預金よりも金利の高い・元本保証されている商品は?
以下の表にまとめました。
| 種類 | 目安の金利 (2025年10月時点) | 利息支払いの タイミング | 引き出し 制限 | 諸経費 (事務コスト・信託報酬) | 利用・購入先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通預金 | 0.2〜0.25% | 年2回 (2月・8月が多い) | <なし> | <なし> | 銀行(ネット含む) 信用金庫 |
| 定期預金 | 0.25%〜1.0% | 満期時に 一括支払いが多い | <なし> *要解約手続き、また中途解約は利率が下がる。 | <なし> | 銀行(ネット含む) 信用金庫 |
| 個人向け国債 (固定3年/固定5年/変動10年) | 固定3年:1.01% 固定5年:1.22% 変動10年:1.08年 | 半年ごとに支払い | <あり> *保有1年経過後は解約可能。 | <なし> | 銀行(ネット含まない) 証券会社 |
| 貯蓄型保険 (学資保険・終身保険など) | 不明(商品による) *保険会社の試算は予定利率で確証がない。 | 満期時に支払い | <あり> *タイミングによっては元本割れの可能性あり。 | <あり> | 保険会社 保険代理店 |
※目安の金利はメガバンクとネット銀行を合わせた数字です。
大きくまとめると普通預金以外に元本保証されている商品は、定期預金・個人向け国債・一部の保険商品の3つです。
定期預金
預ける期間(1年・3年・5年など)を決めて、銀行などに決まった金額を預ける預金。
普通預金と違って、原則満期日(定めた預金期間が終了する日)はお金を引き出すことはできませんがその代わりに普通預金よりも高い金利で預かってくれます。
当面使う予定のないお金(子供の学費・結婚式費用など)は、普通預金で預けておくよりも定期預金の方がお得です。
個人向け国債
国(財務省)が発行する国債を金融機関(銀行・証券会社など)が窓口になって個人にむけて販売している商品です。
金利と保有期間が決まっているのが個人向け国債(固定3年・固定5年)、金利が決まっておらず保有期間が決まっているのは個人向け国債(変動10年)です。
*個人向け国債(変動10年)は国が決める政策金利によって変動します。半年ごとに金利が見直されますので、半年ごとの決まった金利に応じた利息が支払われます。
政策金利が下がればその分貰える利息は減りますが、最低でも0.05%の金利は保証されていますので全く得をしないということはありません。
貯蓄型保険(元本保証に条件あり)
貯蓄と保険がセットになった商品です。
貯蓄型”終身”保険や貯蓄型”学資”保険など、万が一の場合に備えての保険に加入しつつ、支払った保険料の一部を貯蓄できるというものです。
一見便利に見えますが、はっきり言ってデメリットが大きい上に商品としても中途半端なので注意が必要です。
まず一定期間が過ぎる前に途中解約をした場合、契約により貯蓄部分が全額返金されずに元本を割ってしまうリスクがあります。
一定期間加入していれば100%元本保証になる商品もありますが、基本的には途中解約をしないことが前提になるので流動性の面で柔軟性に欠けます。
また保険会社への事務手数料や運用コストなどがかかるので、定期預金や国債に比べて余計な経費がかかる点も見過ごせません。
肝心の利率も特別高いわけではありませんので、デメリットを考えるとあえてこういった保険商品を選ぶ理由も見当たらないというのが正直なところです。
支払われる利息からは税金が引かれることも覚えておこう。

せっかく楽しみにしていた利息、実際に支払われたら「あれ、計算していたよりも少ない気が…」とならないように、支払われる利息にも税金がかかることも確認しておきましょう。
利息には「利子所得」として20.315%の税金がかかる
源泉分離課税 20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)が自動的に差し引かれます。
各商品の例(100万円を1年間預けた場合)
• 普通預金(年0.20%)
税引前:2,000円 → 税引後:約1,593円
• 定期預金(年0.30%)
税引前:3,000円 → 税引後:約2,387円
• 個人向け国債(年1.00%)
税引前:10,000円 → 税引後:約7,968円
計算と合わなくて不安になったら利子所得にも税金がかかることを思い出してください。
個人向け国債>定期預金の順番でおすすめ。
大前提としてはどのくらい預けておく予定かによります。
もし1年だけであれば国債の選択肢は消えますので、普通預金より高い利率を求めるなら定期預金の方がいいでしょう。
まずは余剰資金がどの程度手付かずの状態でも大丈夫か、今後の自分の予定と照らし合わせてみてください。
3年・5年・10年と長期間使わない予定なら個人的には個人向け国債をおすすめします。
参考になれば幸いです。






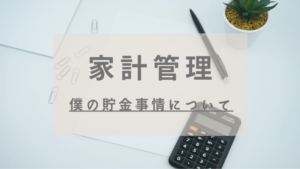

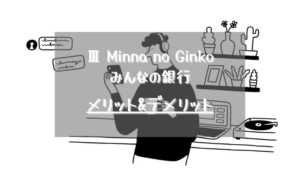
コメント